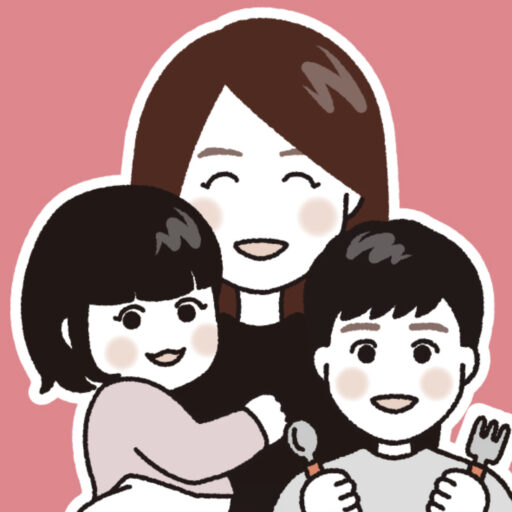Ayumiさん、こんにちは。
ご質問、ありがとうございます。
結論からお伝えしますと、お子さんが食べないときは、他の食べ物は無理に食べさせなくても大丈夫です。
「好きなものばかり食べていたら、わがままになるのでは?」
「栄養が偏るのでは?」
など心配なお気持ちになるかもしれませんが、子どもは、イヤな気持ちで食べたものを嫌いに、楽しい気持ちで食べたものを好きになる傾向があります。
食事の時間を楽しく過ごせるようになると
- 食事量が増える
- 嫌いなものが減る
などの効果が期待できるんですよね。
なので、幼児期は「食事の時間って楽しいな♪」という経験を多く積むことが大切になります。
お子さんに今、
- 体重が増えない
- 身長が伸びない
- 顔色や機嫌が悪い
など、何か心配な様子が見られる場合は、栄養環境の改善が必要になってきます。
しかし、成長に大きな問題がないようであれば、今の成長に必要な栄養はとれていると考えられます。

今すぐ、食事量を増やさないと!食べられる食べ物を増やさないと!などと焦らなくても大丈夫です♪
とは言え、食べてくれないと食事準備が大変ですし、作っても食べてくれないのって精神的なダメージが大きいですよね…。
毎日、お疲れ様です。
そこでここからは、お子さんが食べないとき
- 代表的な原因3つ
- 原因に合った対処法
について、詳しく解説させていただきます。
理由に合った対処法を取り入れることで、解決に向かいやすくなります。
お時間のあるときに、ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです。
食べない主な3つの原因と対処法
お子さんが食べないとき、代表的な原因としては、以下の3つが考えられます。
【原因①】発達段階
実は、2歳前後のお子さんの約50%は、偏食という研究があります。

めちゃくちゃ多いですよね…!!
この年齢で偏食が増えるのは、以下の理由です。
味覚が成長し、味の感じ方が変わる
2歳前後はお口の機能が成長し、1歳代に比べ
- かむ力がアップする
- 口に長く食べ物を入れておく
などができるようになります。
味の感じ方が変わるので、それまで食べていたものを急に食べなくなったり、好みの味のものだけを食べ続けたりするようになることがあります。
歩けるようになり、行動範囲が広がる
行動範囲が広がることで、初めて目にするものが増えます。
子どもにとっては
初めて出会うもの=何が起こるかわからなくて怖いもの
なので、緊張する時間が警戒する時間が増えます。
そのため、安心したい、自分の命を守りたいという本能的な働きから、
- 好きな食べ物
- 食べ慣れたもの
- 見て味がわかるもの
を好み、それ以外のものを食べなくなることがあります。
対策
家族がおいしそうに食べる姿を見せておくのも、効果的です。
家族が食べている姿を見ることで、
「あの食べ物は食べて大丈夫なんだな」
「ママがおいしそうに食べてる…今度食べてみようかな」
など、食への安心感や興味を高めるきっかけになります。

お子さん本人は食べなかったとしても、見て学ぶことも、食経験の1つになります♪
成長し、この時期を過ぎると、何事もなかったかのように食べ始めることもよくあります。
食べ物に対し、良いイメージを持てるようなサポートを意識されてみてください。
【原因②】感覚の問題
子どもの感覚は、大人よりも繊細です。
同じ料理を食べても、大人の2~3倍強く味を感じると言われます。
そのため、以下のような理由で、食べなくなることがあります。
- 食感がイヤ
- 香りがイヤ
- 味が濃くてイヤ
- 味が薄くてイヤ
- 熱い、冷たいのがイヤ
対策
- 食べるメニューの食感に寄せる
- 揚げてサクサクにするなど、食感を変える
- ほおや唇に食べ物を当て、温度を確かめさせてから食べる
- 味付けや香辛料(カレー粉など)を使ったり下処理を工夫したりして(肉や魚は臭み取りをして使うなど)、苦手な香りを軽減する
- 噛んで食べていないお子さんは、噛まなくても味がする濃い味付けのものを好む傾向がある。材料を大きめに切ったり、「どっちが長くかめるか競争しよう」と声をかけたりしながら、噛む回数を増やす工夫をする。
【原因③】学習
食べなかった場合、
- 好きなものを後から出してもらえる
- おやつで好きなものを食べられる
など、学習しているパターンもあります。
対策
- よく食べるメニューは、常に1品以上出しておく
- 食べないメニューは1口程度の少量にして、それを食べてから好きなものを出すルールにする
- 食べなかったら好きなものが出てくると学ばないよう、食べない場合でも好きなものは出さないルールにする
今は「好きなものをおいしく食べる」で大丈夫。食を楽しむ機会作りを
4歳頃になると、お口の成長も落ち着き、言葉でのやり取りもできるようになる(人参は、体にいいから食べようね等の声かけで、食べてくれることが増える)ため、食べられるものの幅が増えてくる傾向があります。
今は先が見えず、本当に食べるようになるの?と不安な気持ちになることもあるかもしれません。
しかし、「食事って楽しいな」と感じる時間を増やしていくことが、将来的に食べられるものを増やすことにつながります。
今は「心の栄養をとっている時期」ととらえ、食べるもの中心の献立作りで大丈夫です。
保育園で食べていると聞くと、
「おうちでも食べて!」
「おうちのご飯がおいしくないのかな…」
という気持ちにもなるのですが、保育園は、先生やお友達の目もあり、おうちとは違う環境です。
保育園では食べるけど、おうちでは食べない!と自分の気持ちをしっかり出せるのは、おうちが安心して過ごせる環境であるからこそなので、ぜひ前向きに受け止めていただけたらと思います。
将来的に食べるものを増やしていくには、様々な食材との接点を作っていくことが大事です。

知っている食べ物や安全だと知っている食べ物は、口に運びやすくなります♪
子どもの好き嫌いは、気分で変わることも多いです。
「食べてみようかな」と思ったときに、挑戦できる環境作りが必要になります。
食べるもの中心の献立で「食事の時間って楽しいな」という経験を重ねつつ、
- 見た目に慣れさせる(調理やお買い物を手伝ってもらう、食べ物が出てくる絵本や図鑑を見せる、食べなくても、週に1回など親子ともに負担にならないペースで食卓に並べる)
- 味や食感、見た目に慣れさせる(口に入れたらほめる、飲み込めなくても吐き出す用の器を用意しておき、吐き出しても良いという逃げ道を作っておく)
など食事以外の時間も使いながら、今は食べない食材との接点も作っていくように意識されてみてください。